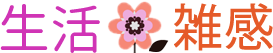毎年年末になるとクリスマスや大晦日、さらにお正月の準備などイベントが盛りだくさんでバタバタと毎日があわただしく過ぎていきます。
そんな中、1年の締めくくりとして欠かせない大掃除はついつい後回しになってしまい、思うように掃除がいきわたらないという経験はありませんか?
今回は大掃除をより効率よく行うためのスケジュールの立て方やポイントなどをまとめてみました。
大掃除はいつから始めるのがいいの?
大掃除は本来「すす払い」として1年の汚れと厄を落とし、きれいな状態でお正月を迎えるために昔から行われてきた習慣です。
12月13日がすす払いの日
そして本来は12月13日がすす払いの日とされており、この日から大掃除をスタートさせて12月28日までには完了させることが習わしとされてきました。
29日~31日は縁起が良くないために大掃除を行うのは適していないとされており、同じく元旦に持ち越してしまうのは穢れとともに福も外へと追い出してしまうといわれています。

自分に無理のないペースで
しかし今はこのような習慣をしっかり守っている方は少なく、できるだけ自分に無理のないペースで始めることが一番重要です。
12月に入るとクリスマスの準備や年賀状の作成など、ほかにもやらなくてはいけないことがたくさんあるため、もっと早くから少しずつ大掃除の準備に取り掛かっていくこともいいでしょう。
ゴミ収集のスケジュールに合わせて
また年末年始はゴミ収集も年末休暇に入ってしまうこともあるので、ゴミ収集のスケジュールも合わせて大掃除の開始日を考えていくことも重要です。

大掃除を始める前にきちんと計画を立てよう!
大掃除はやみくもにスタートしていては思うように作業も進まず、モチベーションを維持していくのも難しくなってしまいます。
イベントが重なる年末時期だからこそ時間を無駄にしないように、掃除を開始する前にしっかりとスケジュールを立てておきましょう。
基本の順番
大掃除を行う順番は内から外、上から下、奥から前の順で行うことが基本です。
この形に添って掃除する部屋や場所を順番に掃除していきましょう。
無理せず少しずつ
1日に全部をきれいにしようとすると、体だけではなく気分も落ち込んでしまうため、無理せず少しずつ仕上げていくことがスケジュールを立てるうえでのポイントです。
計画表やTODOリストを作る
計画を立てる際は、家の中を図にしてわかりやすくしてから、どこを掃除するのか計画表を作っていくのがおすすめです。
またTODOリストを作っておけば一目で自分が掃除した場所がわかるので、モチベーションを維持するうえでも効果的ですよ。

大掃除に使用するアイテムをそろえる
大掃除を始めるときは使用する掃除道具を準備しておくことも、快適な大掃除を行う上では重要です。
汚れを落とすもの
油汚れは酸性なので、アルカリ性の重曹やセスキ炭酸ソーダ、中性洗剤がおすすめです。
皮脂汚れはアルカリ性なので、クエン酸や酢を使えば簡単に落とすことができます。
あると便利なアイテム
他にも、メラミンスポンジやエタノール、割りばし、不要な歯ブラシ、マイクロファイバー、新聞紙など掃除に使用するアイテムはあらかじめ準備しておきましょう。

大掃除はどこから手を付けるべき?
1.まずは不用品の処分
ゴミ収集は年末が近づくと年末休暇に入り、いつものようにゴミを捨てることができなくなってしまいます。
特に連絡ゴミの場合は回収までに時間がかかることもあるので、早めに手配をしておきましょう。
また、家の中に不用品がある状態で掃除を進めるのは非常に手間で、掃除もうまく進まないため、最初にいらないものの分別からスタートが重要です。
2.キッチンから行う
キッチン周りは特に汚れがひどく、時間がかかるため、初めに掃除を行っておくことがおすすめです。
普段は行わない換気扇の掃除やコンロの下の掃除、オーブン内などを掃除していきましょう。
3.水回り
トイレや浴室など水回りの掃除を行っていきます。
気になるカビがあれば、この機会に徹底的に掃除を行ってしまいましょう。
水回りは磨けば非常にきれいになるので、掃除のしがいがある部分でもありますよ。
4.リビング、寝室、子ども部屋など
玄関から遠い順に各部屋の掃除を行っていきます。
エアコンの掃除も忘れずに行いましょう。

5.窓
お部屋の窓も掃除していきましょう。
マンションに住んでいる方の場合、窓を掃除するときは隣や下に住んでいる方に迷惑にならないように気を付けて行いましょう。
6.玄関
最後に玄関の掃除を行います。
靴箱やたたきをきれいにすれば、来客時も気持ちよく迎えることができますよ。

大掃除は計画的に
いかがでしょうか。
大掃除の計画の立て方について、紹介してみました。
年末の大掃除となると、考えただけで気が重くなるという方も多いはず。
BUT しっかりとスケジュールを組んで取り組めばそれだけストレスも小さくなります。
今回の記事を参考に、ぜひ、楽しみながら大掃除ができるといいですね!

毎年やってくる大掃除は、1年の穢れや厄を払い、気持ちの良いお正月を迎えるために欠かせないイベントです。
でも12月はほかにもイベントが多く、バタバタしている中で大掃除も中途半端に終わってしまったり、やり忘れの箇所を見つけてしまったりと後悔が残る場合もあります。
そこで今回は、大掃除をやりきるために心がけたいポイントやコツについてまとめてみました。
大掃除を行うときは計画を立ててから始めよう!
大掃除が失敗に終わる原因の一つに、無計画で始めることがあります。
気持ちばかりが焦ってやみくもに始めてしまうと、のちに時間が足りなくなってしまったり、最後に掃除のしていない箇所が見つかってしまいます。
1番最初にどこからどんな順番で掃除を行っていくかを表にしておくことで、
効率よく掃除を進めることができ、後で見たときもどこを掃除したのかわかりやすくなります。

無理のない計画を立てることが大切
大掃除の計画を立てるときは、ついつい張り切って予定を詰め込んでしまいますが、それはNGです。
1日で終わらせたいと思う気持ちもあると思いますが、普段できない箇所を掃除したり、頑固な汚れを落とすのは時間も体力もかかるため、無理をするとモチベーションも下がってしまいます。
数日で分けて少しずつ
1日ではなく数日で分けて少しずつ進めていくように計画を立てれば、1つ1つの箇所を丁寧に行うこともでき、さらに普段の家事や育児、ほかのイベントの準備にも支障がなく行うことができます。
小さな目標を毎日立てる
そして、計画表に小さな目標を毎日立てることで、達成感もあり、モチベーションを維持しながら楽しく掃除を行うこともあできますよ。
基本的な掃除のやり方
奥から前、上から下、内から外の順に行っていくようにします。
計画を立てる場合も玄関から遠い部屋から順にはじめ、さらにほこりや汚れを上から下に向かって落としていくように勧めていきましょう。

大掃除は家族も巻き込んでみんなで始めよう
大掃除はついついママ一人で行うこともありますが、家をきれいにするのは家族みんなの責任です。
家族に手伝ってもらえる箇所があれば、積極的にお願いして負担を減らしていくことで、大掃除を進めやすくなります。
子どもがある程度大きくなったら、危なくない場所であれば、できる限り掃除に参加してもらうことで家をきれいに保つことや掃除の大切さを学ぶこともできますよ。
必要な道具は最初に用意して楽に進めよう
大掃除で使用する掃除道具は、あらかじめ必要なものをきちんと準備してしまいましょう。
汚れに合った洗剤や道具を選ぶことで、汚れを簡単に落とすことができ、時間を節約したり、仕上がりもさらにピカピカになって達成感もありますよ。
他にも手荒れを防ぐために、ゴム手袋やハンドクリームなどを用意したり、掃除中に汚れることもあるため汚れてもいい洋服を用意しておくことも忘れずに。

完璧を目指さなくてもOK!
ついつい大掃除になるとすべての場所を完璧に仕上げないと気が済まない!という方もいらっしゃるかもしれません。
BUT 1か所に時間をかけすぎたり、集中して掃除を行ってしまうと、ほかの場所がおろそかになって、全体的に見たときにあまりきれいに感じられないこともあります。
どうしても汚れがしつこい場合
どうしても汚れがしつこい場合は、さっと目に見えるところや落とせる範囲の汚れをきれいにして、次の場所へ移りましょう。
ただし、キッチンやお風呂場など良く目につく部分は、ポイントを決めてしっかり掃除を行っていきましょう。

大掃除の後も維持しやすい方法を取り入れよう
せっかく大掃除を行っても、すぐにまた部屋が散らかってしまえば意味がありません。
中には大掃除をしている最中にも、どんどん部屋が散らかって困ってしまうという方もいるかもしれません。
これはそもそも自身に片付けの習慣がついていなかったり、部屋の中が片づけにくい構造になっているのかもしれません。
まずは、出したら元の場所にしまうことを徹底して行っていきましょう。
とりあえずBOX
もしなかなか難しいという方は「とりあえずBOX」を用意して、散らかってしまうものを1つのBOXに入れる習慣をつけてみてはどうでしょうか。
1日の終わりに毎回片づけていけば、部屋の中も散らからずに済みます。
子どもがいる家庭では、それぞれ家族専用のBOXを作ることで、家族が部屋を散らかすことも防ぐことができますよ。
掃除の前にいらないものを断捨離を
また、部屋が散らかるのを避けるためにも、掃除の前にいらないものを断捨離して、ものを減らすことは非常に有効です。
この機会に「とりあえず取ってあるもの」「いつか使うもの」は全部捨ててしまいましょう。


年末に向けてそろそろ大掃除の準備や計画を立てている方もいらっしゃると思います。
年末は大掃除以外にもイベントの準備が重なるので、大掃除も早めに進めることで負担を減らしていくこともできます。
そしてそんな大掃除をより効率よく進めるためにも、まずは家の不要なものを処分し、すっきりした状態で掃除を始めましょう。
今回は、大掃除の第一歩として取り入れたい断捨離のコツやポイントをまとめてみました。

大掃除の前に断捨離をするメリットは?
家の中に不用品がある状態では、なかなか思うように掃除も進みません。
また、大物家具や家電などの連絡ゴミは早めに連絡をしておかないと、年末休暇に入り、大掃除に間に合わなくなってしまうため、大掃除の一番最初にまずは家の中にあるいらないものをまとめてしまいましょう。
自分がどれだけものを持っているのかを把握
断捨離を行うことで、自分がどれだけものを持っているのかを把握ができ、大事なものが何かもわかり余計なものを買わなくなります。
新しいスペースを確保
さらに新しいスペースを確保していくこともでき、新しいものを購入したときもお部屋がごちゃつかず、掃除もしやすくなります。
また、断捨離をしながら整理整頓を行えば、同時に今まで掃除が行き届かなかった場所もきれいにしていくことができますよ。

大掃除の断捨離をおこなう上で気を付けたいことは?
まずは、断捨離を行う基準を自分の中で明確にしておきましょう。
For Example 洋服なら〇年以上着ていないもの、家電なら壊れているもの、今は全く使っていないものなどのラインを決めて捨てるものと残すものに分けていきます。
新しいものや、高かったものは
中にはまだ新しいものや、高かったものなど捨てにくいと感じるものもあるかもしれませんが、それよりも自分の中で使わないもの、不要なものと感じたら思い切って断捨離していきましょう。
捨てた後に後悔しないために
しかし基準を明確にしないままあれもこれもと捨ててしまうと、捨てた後に後悔もあるので絶対に残しておきたいものも明確にしておきましょう。
家族のものは層談してから
また、家族のものはどんなものであっても勝手に捨てるのではなく、一度相談してから処分するようにしましょう。
あなたにとってはいらないものBUT 本人にとっては大事なものや思い入れのあるものであった場合、取り返しがつかなくなるので気を付けていきましょう

断捨離を行うときはまずすべてのものを出していく:大掃除の基本
断捨離を行うときは、まず断捨離をするカテゴリーのものをすべて一度出してすべてのものが目に見えてわかりやすい状態でスタートしましょう。
こうで自分がどれだけの量を持っているのかを把握ができ、一度にいるもの、いらないものに分けていくことができます。
いるものといらないものを分ける
大きなビニール袋などを2つ用意して、いるものといらないものにシンプルに分けていきましょう。
すべてものの仕分けが終わったら収納場所の掃除を行い、再びいるものを収納していけば一気に掃除も整理整頓も終えることができます。

大掃除の断捨離後、不用品の中からさらに仕分けていく
断捨離で不用品を選別したら、その中からさらに細かく分けていく作業も行いましょう。
- 捨てるしかないもの
- 誰かにあげるもの
- 販売可能なもの
…などに仕分けてそれぞれ処分していきます。
捨てるしかないと判断したもの
捨てるしかないと判断したものは、速やかにそれぞれの住んでいる地域のゴミ収集のルールをもとにゴミに出すようにします。
誰かにあげるもの
処分品の中からもらってくれそうな人がいるのであれば、年末の忙しい時期は避けて早めに連絡をしましょう。
販売可能なもの
販売可能なものは、リサイクルショップやメルカリなどに出品すれば、年末の臨時収入につながる可能性もありますよ。
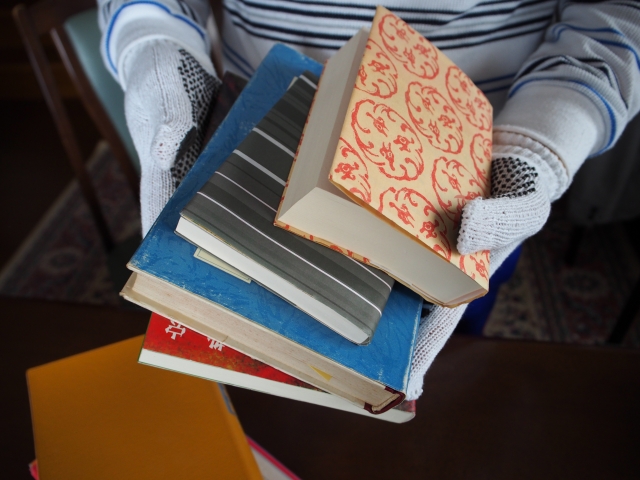
大掃除の断捨離後は、余計なものを家にため込まない習慣を
大掃除のタイミングで断捨離を行えば、家の中が目に見えてすっきりして、日ごろから掃除や整理整頓がしやすい空間を手に入れることができます。
しかしだからといって、空いたスペースを当てにしてまたあれもこれもと買い物を続けてしまっては、また家の中に物があふれてしまい、せっかく断捨離や大掃除をした意味がなくなってしまいます。
普段からいらないものはすぐに捨てる習慣を
断捨離を行うことで、自分に今何が必要なのか、今までどんな余計なものを購入してきたのかがわかると思うので、それをもとに今後は生活をしていきましょう。
家にいろんなものを置かない
普段からいらないものはすぐに捨てる習慣を身につけ、もったいないと家にいろんなものを置かないようにしましょう。
一時保管の箱
また迷った際には、専用のBOXを用意して一時保管をしておけば、その後の断捨離はより簡単に行うことができるのでぜひ大掃除のタイミングで取り入れていきたいですね。