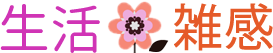おせち料理 令和4年
来年2022年は令和4年:お正月を迎えます。
お正月にはかかせないおせち料理を構成する具材の種類は一般的に約20から30種類といわれそれぞれに意味があるとされています。
ですが、現代の家庭ではこれだけ多く一から手作り作りするのは大変です。
なので最近では、一部は手作りするが他は購入して用意するという家庭が多いようです。

おせち料理には、それぞれ縁起かつぎの意味や由来があります。
たとえばおなじみの紅白かまぼこは、名前には紅白という言葉が使われていますし見た目は日の出を象徴するものだそうです。
今年は縁起をかつぎながら自分でも作れそうなものにチャレンジしてみてはいかがでしょうか?

お正月に食べる料理といえば『おせち料理』ですよね。きっと多くの人がおせち料理を食べた経験があると思います。
ところで、なぜ正月にはおせち料理を食べるのでしょうか?もしかしたら、パパやママの中には、お子さんからそのような質問をされたことがある人もいるかも知れません。
お子さんからそのような質問をされたときでも困ることが無いように、おせち料理の意味や由来を紹介します。

おせち料理とは??
そもそも、おせち料理とは何なのでしょうか?
御節料理
おせち料理は、漢字で「御節料理」と書き、その始まりは、正月や五節句などの節目ごとに、収穫や豊作を神さまに感謝して供えたお供え物を「節供(せちく)」と呼び、節供として神さまにお供えされた作物を料理したものを「御節料理」と呼ばれていました。
おせち料理の由来
このときの「御節料理」が現在のおせち料理の由来とされています。
五節句とは
ちなみに、五節句とは、『人日(じんじつ)の節句:1月7日、上巳(じょうし)の節句:3月3日、端午(たんご)の節句:5月5日、七夕(しちせき)の節句:7月7日、重陽(ちょうよう)の節句:9月9日』と呼ばれる節日の事で、この日に邪気を払うための宴会が催されていました。

おせち料理の歴史は?
「御節料理」としての風習は弥生時代からありましたが、おせち料理が定着したのは、奈良時代から平安時代にかけてで、宮中行事として節の技師位が執り行われるようになり、その時に「御節供(おせちく)」と呼ばれるお祝いの料理が振る舞われていました。
正月だけではなかった
この頃は、おせち料理を「正月に食べる」という現在の風習ではなく、五節句に出された料理は、毎回「御節供」でした。
庶民の間に
江戸時代になると、宮中行事であった「御節供」が庶民の間にも広まりました。
重要な日の料理として
5節句には、豪華な閭里が振る舞われていましたが、その中でも1年のうち最も重要とされる人日の節句に振る舞う料理が、正月のおせち料理として定着しました。
江戸後期から
江戸後期には御節に入る料理一つ一つに意味を込め、家族が揃っておせち料理を食べるという風習ができました。

おせち料理に決まりはあるの?
正式に言うと、お重の数は四段で、以下のものを詰めるという決まりがあります。
一の重(一段目)「祝い肴と口取り」
二の重(二段目)「焼き物」
三の重(三段目)「酢の物」
与の重(四段目)「煮物」
最近の主流
この決まりは絶対というわけではありません。実際、最近流通しているおせち料理は三段のものが主流だったり、酢の物をほとんど入れず、焼き物が多く詰められたものも多いですよね。
決まりに沿ったものを
御節に詰められる料理には、それぞれ意味があるので、お重の数は別としてもせっかくなので、お重に詰める料理は、昔からの決まりに沿ったものを詰めたほうがいいかもしれません。

おせち料理に使う食材とその意味は?
地方や各家庭で、食材や詰め方などは多少異なると思います。ここでは、代表的なものを紹介します。
一の重
- 紅白かまぼこ
半月型の形は日の出・慶び(赤)・神聖(白)の意味。 - 栗きんとん
金運と勝負運への願い。黄金色をした栗きんとんは財宝に例えています。・数の子:「子孫繁栄」への願い。にしんの卵は、数が多くそれにあやかるため。 - 田作り
五穀豊穣への願い。片口いわしを肥料として田畑に撒くと豊作になったことにちなんでいます。 - 黒豆
邪気払いと勤勉(まめ)に働くこと、丈夫に過ごせることへの願い。 - たたきごぼう(きんぴらごぼう)
その土地に末永く繁栄するようにとの願い。ごぼうが地中深くまで根を張ることからそれにあやかるため。 - 伊達巻
知識が増えるようにという願い。昔の書物は巻物にされていて、形がその巻物に似ているため。 - 昆布巻き
健康長寿への願い。「よろこぶ」に掛けたゲン担ぎ。

二の重
- 焼き魚(ブリ)
出世への願い。ぶりが出世魚であることに掛けています。 - 焼き魚(鯛)
「めでたい」という言葉との語呂合わせ。縁起物として出された料理。・エビ:長寿への願い。海老は腰が曲がり、長いひげがあることから、海老のようになるまで長生きしたいという願いを込めています。

三の重
- 紅白なます
平安や平和への願い。なますの赤(人参)と白(大根)は水引をかたどっています。

《与の重》
煮物に使う具材は、山の幸を中心に使われています。
- れんこん
将来への見通しへの願い。れんこんに穴が空いている事にあやかります。 - 里芋(八つ頭)
子孫繁栄への願い。里芋が地中でたくさんの小芋を作ることにあやかります。 - くわい
出世への願い。くわいは、大きな芽を出すことから込められた願いです。また「芽出たい=めでたい」とした語呂合わせによる縁起物としても使われています。 - こんにゃく
良縁、夫婦円満への願い。おせちで使うこんにゃくは、真ん中がねじれている「手綱こんにゃく」を使います。これは、真ん中のねじれを結び目に見立て、それと縁結びをかけて良縁や夫婦円満への願いが込めれられています。 - しいたけ
長寿への願い。長寿の象徴である亀の甲羅に見立てられ使われました。

今回は、正式なおせちのマナーに沿って与の重まで書きましたが、主流となっている三重のお重を使う場合、一の重は同じですが、二の重に酢の物と焼き物、三の重に煮物を詰めます。
まとめ
おせち料理というのは、重箱の数にも使われている食材にも様々な願いが込められた日本の伝統的な料理だということがわかりました。
現代では、ライフスタイルに合わせて上に上げた食材が使われていなかったり、中には作るのが大変ということで、正月におせちを作らなかったり食べなかったりという家庭も増えてきていると思います。
ただ、今は様々な企業がおせち料理を販売し、それを通販等で買うことも出来ます。
日本の伝統的な「おせち料理」を囲み、その歴史や意味をお子さんたちに伝えてみてはいかがでしょうか?

令和のおせち料理:定番具材の種類と意味10選
紅白かまぼこ
おせちといえば紅白かまぼこは外せません。めでたい紅白と初日の出を象徴しています。
かまぼこは切るだけですが、様々な飾り切りなどを施すと華やかになるので試してみてはいかがでしょう。
伊達巻
長崎発祥のカステラ蒲鉾が伊達巻として流通しました。お洒落、華やかという意味の伊達と学問に通じる巻物を見立てて作られたとされています。手作り方法もネットで調べられますので、最近は手作りする方が増えてきたようです
錦玉子
金銀、錦に見立てられているという説と、黄色と白の二色で錦をかけているともいわれています。
錦卵は伊達巻と兼用して省略したり、簡単に厚焼き玉子で代用する方もいるようです。
紅白なます
紅白の水引を模しているともいわれる縁起物の一品で、大根と人参の千切りで酢の物を作る方が多いようです。
田作り
五穀豊穣を祈るもので田んぼの肥料として小魚を撒いていたことから名づけられたようです。市販の少量を購入する方が多いようです。地域によって小魚の種類も変わります。
黒豆
まめに働くとかまめに暮らすという意味が込められているとされています。時間をかけて手作りする方も多いようで、あえてシワを寄らせて作る地域もあります。

数の子
子孫繁栄や子宝の象徴とされています。市販の塩カズノコや、すでに味付けされた数の子が利用されているようです。

海老
見た目の豪華さや朱の彩はもちろんですが、腰が曲がるまで長生きするという長寿の願いが込められています。ボイルして添えるのが一般的のようです。イセエビやロブスター、エビグラタンを利用する方も多いようです。
昆布巻き
喜ぶから語呂合わせで使われるようになったというのが定説のようです。こちらも市販のパックを利用する方が多いようです。
鯛
こちらも語呂合わせで目出度いから鯛が使われるようになったようです。すでに調理済みの鯛が市販されていますので、購入して添える方が一般的です。
令和のおせち料理:購入のポイント
上記で記載した定番の10品は、年末のスーパーや食料品店では必ずと言って販売される定番の品です。
ローソンストア100
年末も仕事で少人数分だけ用意する方には、100円ローソンの限定おせちがおすすめです。
毎年クリスマスころに全29品が販売され、すぐに完売してしまいます。以下は2019年のラインナップです。
ワカサギ/あさり/えび甘露煮/塩カズノコ/味付けカズノコ/あぶり焼き合鴨スライス/かまぼこ白/かまぼこ赤/ふぐ蒲/伊達巻/寿なると/寿なると赤/鮭昆布巻/鰊昆布巻/一口鰊昆布巻/つぶつぶ栗きんとん/栗甘露煮/黒豆/厚焼きたまご/田作り/数の子松前/いか明太/いか黄金/つぶ貝わさび/ほたてわさび/わさび本漬/切り千枚/なます着/鯛づくし
業務スーパー
伊達巻、かまぼこ赤、白、昆布巻き、黒豆は高確率で入手できます。
ほかに、田作りや紅白なますなども時期になると店頭に並ぶのでのぞいてみてはいかがでしょうか。

令和のおせち料理:豪華な一品を添える
市場で購入
名物のアメ横や豊洲市場は有名ですが、地元の市場に足を延ばして正月の豪華な一品を購入するのはいかがでしょうか?また、大人数や数日分の用意をするのなら、この機会にコストコなどの郊外の量販店を利用してみるのも安上がりにできるかもしれません。
ネット通販
お正月に豪華にカニやイセエビを用意するのなら、ネット通販のカニがおすすめです。また、年末になるとテレビショッピングの虎ノ門市場なども評判が良く毎年恒例となっています。
産地直送通販
各地の協同組合や鮮魚店で独自のホームページで通信販売を行っている場合があります。インターネットで検索すると簡単に見つけることができますので利用してみてはいかがでしょうか?
令和のおせち料理:まとめ
2019:令和のおせち料理
家族が楽しむおせち料理ですが、すべてを手作りするのは大変ですし費用もかさんでしまうかもしれません。
わりきって市販品も上手に利用して我が家の素敵なおせちを作ってみませんか?
また、仕事が入ってしまったり家族が離れている場合、来客の予定がある場合などは専門店のおせちを購入してみるのも良いかもしれません。
ネット通販の場合ですと、早期割引がお得ですし、人気があるおせちは早期完売になる場合もありますので一度チェックしてみることをおすすめします。
来年のお正月が貴方にとって素晴らしい年の始まりになりますように。
ここまで読んでいただきましてありがとうございました。